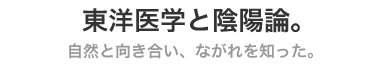陰陽論 の起こり
太陽があり、生命は育まれる。
古代中国で自然の観察とは四季の観察でした。
そして、それに最も影響している太陽の出と入をみつめました。
日中には陽の気が増え、夜中には陰の気が増えている、
このように捉えたことで、一日や四季の理解を深めていったのです。
つまり、陽の気と陰の気のバランスの変化を考えること、
それが陰陽論の始まりでした。
![]()
四季を陰陽で考える
一年では立春から春になります。春は昼間の時間がだんだんと長くなり、植物の芽が葺くことから、春は多くの陰の力に対し、僅かずつ陽の力が増えていく時期と捉え、生命の成長の時期と考えました。
立夏からの夏は、昼間の時間が長い時期であり、植物の開花の時期、つまり陰の力よりも陽の力が多くなる、生命の発展の時期と考えました。
さらに立秋からの秋は、夜の時間がだんだんと長くなる、つまり陽の力が多い状態から、徐々に陰の力が増えていく、植物の収穫の時期、つまり生命の壮年の時期と考えます。
そして、立冬からの冬。この時期は、夜の時間が最も長くなる時期を含み、植物が種を落とし、種が地中に埋もれる時期、つまり陰の力が陽の力よりも多くなる生命の終焉の時期と考えます。
自然の様々な状態は、陰陽のバランスの変化からみつめてみますと、自然の共通の原理を考えることができる。そして、ここに生命活動の理解や生命循環の思想も育くまれたのでした。
さらに、身体についても陰陽論で観察されるようになったのです。
![]()
身体の陰陽論とは
陽の溢れる日中では、人の身体からは生命が溢れ、躍動感が生まれ、活動的になります。これは昼に溢れる発散する力の作用。逆に陰の広がる夜中では、生命が休まり、動作は落ち着き、休息的になります。ここで作用するのは夜を取り巻く収束する力。つまり、発散する力を陽、収束する力を陰と名付ければ、一日あるいは一年で、身体へは陰陽のバランスの変化が絶えず影響している、と考えられるのです。
発散と収束という、相反する対極の状態に陽と陰という名を付け、この陰陽が平衡がとられながら連続的に作用することで生まれる変化・関係を見つめると、そこから自然、あるいは生命の動的変化が捉えることができる。
つまり、ある双極間で同位同時に存在する、動的な相対的な関係性から生命を捉えなおすこと、これが陰陽論なのです。
さて、「ながれ」。
このながれという言葉には生命の躍動が現れていますが、水が高きより低きへ流れるように、ある存在に作用している陰陽(水に対しての高さのエネルギー)を観察し、その陰陽の差から生まれるのが「ながれ」(水は川となる)だと考えるようになったということです。
自然に存在する「陰」と「陽」の状態と、その差から生まれる「ながれ」。
その差が生まれないような、つまり陰か陽のどちらかに偏った状態、あるいは、陰も陽もなく均一化された状態のなかでは、「ながれ」は失われ、身体ではそれが病、あるいは死につながると考えられるのです。
![]()
身体の「ながれ」、気血と経絡
さて、身体をながれる気血を陰陽論から捉えてみますと、身体の気は上がりやすく血は下がりやすい、ということから、気は血に対し陽性で、血は気に対し陰性となります。その性質のまま気血を放置し、その分離が起これば身体の機能を担えなくなり生命を持続できません。ですから経絡によって、気や血を偏りなく巡らすだけでなく、上下に分離することなく全身へ分配し身体の機能を維持する必要がある、と考えたのです。
しかし、経絡に何らかの変動が生じると、その気と血の陰陽のバランスが崩れるため、気が上がり、血あるいはそこに含まれる水分は下がることになる。気が上がれば、頭や頚肩などに腫れや痛み、熱などが発生し、血や水分が下がれば、身体の腹部・腰部や下肢にむくみやだるさ、冷えが発生する。
この状態が続くことから疾病が始まる、つまりこれが「未病」だと東洋医学は考えたのです。
東洋医学に陰陽論。ここにとても大切な関係がありました。